従業員を降格処分にする場合、基本的には、労働者の承諾や就業規則や労働契約上に根拠がなくても、役職や職位を引き下げることはできます。
とはいえ、このような人事権を無制限に認めてしまえば、事業主の好き放題になってしまいます。
そこで、降格処分を行うにも法的な制限があるわけですが、その線引きを踏まえて就業規則を作らないと、ただでさえ不満の元になる降格処分が、労使トラブルの発端になってしまいます。
降格処分には適正な運営ルールを
降格処分は、事業主の経営判断として裁量が認められていますが、やはり無制限に許されるものではありません。
行き過ぎた降格処分は、権利の濫用として無効とされます。
一般的に降格処分になれば、不満を抱えるのが人の感情です。
そこに、嫌がらせ・みせしめ・退職目的など恣意的なものがあれば、一気に労使トラブルへ発展してしまうことも考えられます。
降格処分のルールを理解して、労使紛争にならないように人事制度を運用していかなくてはいけません。
降格処分が認められる3つの基準
降格処分が無効になる場合とは、社会通念上妥当性を欠き、権利の濫用と認められるケースです。
具体的には、次の基準によって総合的に判定されます。
- 使用者側における業務上、組織上の必要性の有無及び程度
- 労働者の能力又は適性の欠如の有無及び程度
- 労働者の受ける不利益の性質及び程度等の諸事情
これらの事情を総合的に判定し、降格処分が権利の濫用にあたるかどうかが決まります。
2種類に分けられる降格処分
まず、降格処分には、
- 懲戒処分としての降格(従業員の規律違反や秩序違反に対して行われる降格)
- 人事権の行使としての降格(従業員の適性や成績に対して行われる降格)
の2種類があります。
人事権の行使としての降格は、原則、従業員の承諾や、就業規則や労働契約に根拠がなくても、行うことが認められています。
それに対し、懲戒処分としての降格は
- 就業規則に当該懲戒処分の根拠規定が存在する
- 労働者の問題行為が当該就業規則上の懲戒事由に該当する
- 懲戒処分につき、客観的合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる
場合に有効と判断されます。
懲戒処分としての降格の方が、厳格なルールが適用されるといっていいです。
懲戒処分としての降格と人事権の行使としての降格には、このような違いがあることを認識しておきましょう。
2つの降格処分を同じに考えてしまうと、労使トラブルに発展しやすくなります。
人事権の行使としての降格処分が無効とされた判例
ここでは、人事権の行使としての降格処分が無効とされた判例を見ていきます。
1.広島精研工業事件
この事件では、課長職にあった従業員が、降格処分を受けて6段階下の平社員まで下げられた事例です。
会社側の降格理由は
- 安全・品質に関する成績の不良
- 教育能力の不足
- 管理指標に関する基礎知識の不足
- 対人関係のトラブルの多さ
を挙げています。
これついて裁判所は
「安全・品質に関する成績不良については、課長である従業員にも責任の一端があり、課長からの降格処分もあり得る」
としながらも、
「平社員まで大幅に降格させる必要性があったとは認めがたい」
としています。
また、役職手当6万円が降格で不支給になることについても、
「賃金の約15%もの減額となることからすると、その不利益の程度は重大である」
ともしています。
これらの事情から、降格処分は権利の濫用に当たるとの判断がされました。
ちなみに、②~④の降格理由については、②と③の評価は相当といえず、④の事実関係を裏付ける証拠もないとしています。
2.ニチイ学館事件
ニチイ学館事件は、営業成績が不振と理由とする降格処分が無効となった判例です。
この降格処分では、3段階の降格、約45%の減給という内容が問題と指摘されています。
この降格処分について裁判所は、
「経緯に照らすと、本件降格までの原告の勤務状況によって、原告に対してこのような大きな不利益を与えるまでの相当性があるとはいえない」
として、権利の濫用として無効としました。
降格処分が認められる2つのポイント
2つの判例を読むと、
- 大きな減給
- 大きな降格
が問題とされています。
従業員の適性や評価を理由に降格処分を下す場合でも、いきなり大きく減給・降格することは避けるべきといえます。
もちろん実務的にも、段階的に進めていくことが、労使トラブルに発展することを防止する手段となります。
大幅な賃金の減額、役職・職位の降格とされないためには
降格処分には、懲戒処分による降格と、人事権の行使による降格の2種類があることは先に述べました。
懲戒処分による降格の場合、労働基準法91条が適用され、降格に伴う給与の減額には限度額の規制が課せられます。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働基準法91条
その一方、人事権の行使による降格による減額の場合は、労働基準法91条には抵触しません。
しかし、判例で見た通り、15%の減額で従業員の不利益は大きいと判断していることを忘れてはいけません。
また、減額が制裁目的や退職目的とされないようにするために、下記の注意点を守る必要があります。
- 役職ごとの賃金基準が定められた賃金規定がある
- 会社の一方的な裁量で行われてない
- 就業規則の定めに、降職・降格の区分が定められている
- 就業規則に、当てはまる懲戒事由が定められている
- 合理性や相当性のある処分である
以上のことから考えても、給与の減額は小さな段階を踏んで行う方が安全といえます。
なお、階級の降格については、2段階以上下げると、人事権の権利の濫用とされる可能性が高くなります。
懲戒処分の降格には必要な手続きを入れる
懲戒処分に行うにあたり、必要な手続きを怠ると、無効とされる怖れが出てきます。
たとえば、事業不振による整理解雇の無効を訴えた日本通信事件では、整理解雇の対象者となった従業員の選定方法に、手続き上の問題があるとして、無効とする理由の一つに挙げました。
問題とされたのは、退職勧奨に応じなかった3人の従業員を指名したうえで、各人の個別の事情に配慮することなく、整理解雇の対象者としたことでした。
これでは、職勧奨を拒否した人間を単に指名しただけだろう、との印象を与えてしまいます。
このような、ヒアリング等の必要な手続きを省いてリストラ対象を選ぶことは、労働契約法16条にいう「客観的合理的な理由」を欠くことになり、解雇権を濫用したとみなされてしまうのです。
上記は解雇という重い処分の場合ですが、降格処分を行う場合も同様に、必要な手続きを踏むことで、労使紛争になった際に正当性を裏付ける主張になるでしょう。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法16条
懲戒処分の降格には従業員の弁明の機会を設ける
ちなみに、判例の中には、けん責のような軽い懲戒処分でも、従業員に弁明の機会を与えるべきというものがあります。
「懲戒処分に当たっては、就業規則等に手続的な規定がなくとも格別の支障がない限り当該労働者に弁明の機会を与えるべきであり、重要な手続違反があるなど手続的相当性を欠く懲戒処分は、社会通念上相当なものといえず、懲戒権を濫用したものとして無効になるものと解するのが相当」
軽い懲戒処分でも、いちいち弁明の機会を設けるのは、実に面倒な話と思われることでしょう。
しかし、このような判例がある以上、手続きに瑕疵があれば、それを問題とされる怖れがあるということです。
やはり、軽微な懲戒処分の場合でも、従業員に弁明の機会を与えるべきといえるでしょう。
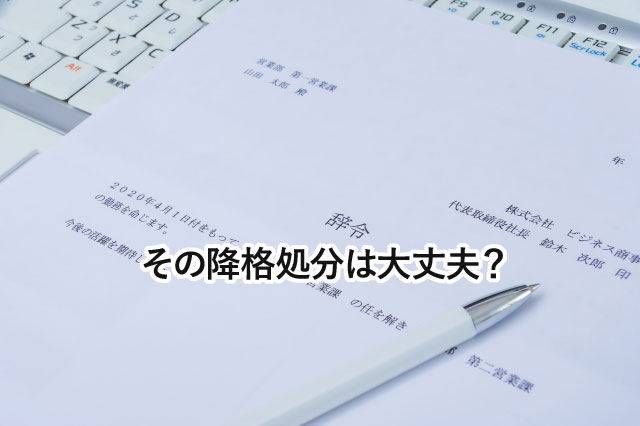


コメント