従業員が定期健康診断を受けることは、労働安全衛生法で義務付けられています。
従業員が長く元気で働けることは、会社にとっても利益になります。
ただ年齢も40歳を超えてくれば、いろいろと病気も出てきますので、定期健康診断だけでなく、人間ドックの健康診断も取り入れたいとことろです。
では、定期健康診断や人間ドックを行った場合、税務上の取り扱いはどうなるのでしょう。
結論からいえば、要件を満たすことで「福利厚生費」として計上できます。
健康診断をしない会社には罰則あり
健康診断は法律的に義務となっており、労働安全衛生法第44条に実施義務が制定されています。
労働安全衛生法違反の場合は50万円以下の罰金刑があります。
労働者の健康を守ることも大事ですが、健康診断を実施しないことに罰則があることも注意点です。
健康診断の種類
健康診断には特殊健康診断と一般健康診断があります。
一般健康診断
「一般健康診断」は職種に関係なく実施する健康診断で、すべての企業が対象になります。
雇い入れ時の健診や、1年以内ごとに1回実施する定期健診のほか、海外に6カ月以上派遣する労働者を対象とした健診や、給食従業員の検便なども含まれます。
特殊健康診断
法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければならないとされている業務は、高気圧業務、放射線業務、特定化学物質業務、石綿業務、鉛業務、四アルキル鉛業務、有機溶剤業務です。
法律で定めのある健康診断の11項目
- 既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査
- 自覚証及び他自覚症状の有無の調査
- 身長、体重、視力、聴力、腹囲の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖値検査
- 心電図検査
- 尿検査
健康診断の対象者
労働安全衛生法上の健康診断は、「常時使用する労働者」に対して受診させなければならないとされています。
正社員
期間の定めのない契約により働いているものになります。
契約社員等
更新により1年以上働くことが予定されているもの、及び更新により1年以上働いているものになります。
パート・アルバイト
その会社で同じ業務に従事している社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上働いていること。
ただし、2分の1以上働いているパート・アルバイトに対しても実施することが望ましいとされています
役員
役員も従業員ですが、適用される役員とされない役員がいます。
たとえば常務取締役兼任工場長といった労働者性のある役員の場合は、健康診断の実施対象になります。
反対に、代表取締役社長のように事業主の場合は、健康診断実施義務はありません。
健康診断導入で助成金の対象に
ちなみに、キャリアアップ助成金の「健康診断制度コース」を利用すれば、有期雇用の従業員(非正規社員)に対して、法定外の健康診断を新設・導入した事業主が助成金が支給されます。
こういった助成金を使えば、費用の負担を軽減して健康診断を導入できます。
健康診断の費用を「福利厚生費」にするための3つの条件
健康診断の費用を「福利厚生費」に計上するためには、次の3つの条件を満たさなくてはいけません。
- 全従業員が対象であること(一部検診について年齢で区分することは可能)
- 健康管理を目的としたもので高額でないもの
- 料金を会社が負担し、会社が直接診療機関に支払っていること
上記3つの条件を満たすと福利厚生費として経費にできます。
反対に3つの条件を満たさない場合は、従業員への「給与」となります。
1・全従業員が対象
福利厚生費とするには全従業員が健康診断を受けることが条件です。
全従業員には役員も含まれます。
ただし特定の役員のみを対象とした健康診断の費用を会社が負担したときは、その役員への賞与とみなされます。
賞与ですので損金計上できませんし、個人へは所得税・住民税が課せられます。
健康診断は「40歳未満は定期健診、40歳以上は人間ドックによる健診」や「雇用期間が3年以上経過した従業員を対象とする」といった、年齢や条件に応じた区分を設けることも可能です。
2・健康管理を目的としたもので高額でないもの
健康診断の費用は高額なものだと福利厚生費として認められなくなります。
その目安は、一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、福利厚生費として処理することができます。
3・料金を会社が負担し、会社が直接診療機関に支払っていること
健康診断の費用は、会社が診療機関に直接支払う必要があります。
そのため、会社が従業員に健康診断費用を渡し、社員が診療機関に支払った場合は給与となります。
たとえば従業員から「会社指定の病院ではなく、かかりつけの病院で受診したい」といった要望を受けた場合です。
従業員が自分の好きな病院で健康診断を受け、その費用を一時的に立替え、あとから会社に請求して精算すると、それは給与になります。
税務調査では健康診断の実施ルールについて、就業規則に書かれているかチェックされることがあります。
就業規則を整備して、健康診断の実施基準を明確にしておきましょう。
人間ドックは福利厚生費になるか?
人間ドックの場合も、福利厚生費として経費にできます。
ただし、上記の3つの条件を守る必要があります。
国税庁のホームページでも人間ドックについて照会されたケースを公開しています。
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。
この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
引用元:人間ドックの費用負担
役員のみが人間ドックを受診していて税務調査で否認されたという例もご紹介しておきます。
この場合、社内規定に「役員のみが受診できる」と記載されていても否認されます。
まとめ
健康診断・人間ドックが福利厚生費として経費になるかについて解説してきました。
ポイントは、全社員が受けること、高額でないこと、診療機関に直接会社が支払うこと、という3つを守れば、健康診断も人間ドックも福利厚生費で経費にできます。
参考にしてみて下さい。
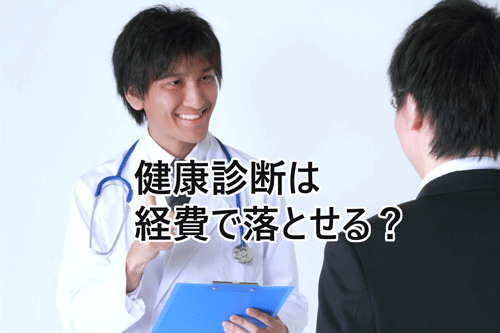


コメント