この記事でご紹介するのは、非常勤講師が大学から受取った報酬を「雑所得」で申告し、それを税務署から「給与」と否認され、裁判で争った事例です。
結果からいうと、裁判所の判決でも、非常勤講師の報酬は「雑所得」ではなく「給与」とされました。
・非常勤講師が大学から受取った報酬が「給与」と否認された事例
なぜこの事例を紹介するかというと、「給与所得の定義」がよくわかるからです。
これから業務委託や請負契約で、個人事業主やフリーランスに外注しようとお考えなら、給与にされないよう、「給与所得の定義」を理解し、その線を超えないようにしなくてはいけません。
その給与所得は、シンプルにまとめるとたった2つです。
それがこの事例から学べます。
「外注費」と「給与」の違いをしっかり理解するなら、下記リンク先記事が役立ちます↓
非常勤講師の大学から受取った報酬が「給与」と否認された事例
非常勤講師の主張
非常勤講師は、「大学から受取った報酬は、所得税法上「雑所得」となるものであって、「給与所得」ではない」と主張しました。
その根拠は次の通りでした。
※給与所得の判定に関係する部分だけ抜粋します。
1.常勤の講師の給与と違い、固定制・継続性がない。
- 講義の時間数で報酬が決まり、休校・休暇になると原則減額される。
- 賞与も支給されない。
- 病気等の理由で休講になれば直ちに手当を打切られる。
2.非常勤講師の地位は大学側と「従属的服務関係」にあるとはいえず、業務遂行にあたっては「自己の計算と危険」は非常勤講師の負担となる。
- そもそも非常勤講師は、常勤講師と次の違いがあるから、非常勤講師の報酬と常勤講師の報酬を同じにするのは間違い。
- 健康保険をはじめ、失業保険、厚生年金保険等の各種保険の対象とされず、共済組合の組合員資格もない。
- 労使関係を前提とする職員組合の組合員にもなれず、就業規則の適用下になく、また、退職金も支給されない。
- 担当する講義に対して実質的に経費に該当する研究室、研究費等は一切与えられない。
- 教授会への出席権も出席義務もなく、ただ大学が定めたカリキユラムの一部を委嘱されるにすぎず、その編成義務もない。
- このことからも、非常勤講師は大学側と「従属的服務関係」にあるとはいえず、独立した主体といえる。
3.第三者に委託できるかの代替性について
- 非常勤講師の講義内容は、スペイン語、比較文学等専門分野における知識の提供であり、その労務内容は非代替的な性格を有するものであって、もともと「従属的服務関係」になじまない。
- 以上のように、大学の委嘱する講義を担当することに関しては従属的ではあっても、大学との関係は本質的に独立的である。
4.雑所得で申告した理由
一応、雑所得で申告した理由も記載しておきます。
- 一般に「講演料」と呼ばれる収入は雑所得とされている。
- 非常勤講師料は実質において講演料と同じ性格のものであるから、雑所得で申告するのが正しい。
給与所得の定義はシンプル
まず、給与所得が法律でどう定義されているかを理解しましょう。
所得税法 第28条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。
上記の「これら性質を有する給与」とは、単に雇用契約に基づいて支払われる報酬だけでなく、たとえば、役員が会社と交わす委任契約で支払われる報酬も給与して取り扱われています。
いい換えれば(委任契約や請負契約の場合でも)
- 労務の提供が自己の計算と危険によらず
- 他人の指揮監督下に置かれて、その対価として受取る報酬
が給与所得となる2つの要点です。
それはつまり、非常勤講師が主張するような、
「雇用関係に固定制・継続制がない」
だけで、「給与所得にならない」と決まるようなものではないですし
「専門分野における知識の提供であり、その労務内容は非代替的な性格を有するもの」
であっても、提供する労務が、雇用契約等に基づいた「指揮監督下」で提供されたものであるなら、支給した名目はどうであっても「給与所得になる」のです。
こうした給与所得の解釈をもとに、裁判所は次のように判断しました。
裁判所の判定
1.指揮監督について
大学側は、大学が必要と認めた学科目について、委嘱の期間、担当日、担当時間数を定あて非常勤講師にその学科目の講義を委託し、これに対して所定の報酬を支払うことを約束した。
非常勤講師は、その約束に従って、週の内、特定の科目、特定の時間、特定の場所で、ある程度の継続した期間、大学の授業を行っていた。
これは大学の一般的指揮監督に服するものというべきである。
2.自己の計算と危険において独立して営まれていたかについて
大学側は非常勤行為の報酬として、常勤講師とは別に、支給規程を設け、その規定に従って報酬を支払っていた。
その手当については、夏季、冬季等の休暇中でも支給され、休講等があっても減額されることがなく、講義内容の優劣等はその増減の対象となっていない。
これは自己の計算と危険において営まれているとはいえない。
総合判断
以上ような勤務形態を前提とすれば、本件手当は、非独立的に提供される労務の対価たるもので、その労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮監督ないしは教員組織の構成員としてその支配に服してなされるものとして、給与所得に該当すると認めるのが相当である。
非常勤講師の主張への反論
非常勤講師の主張に対する反論も述べられていましたので、こちらも記載しておきます。
A. 手当が固定性・継続性を欠いていることについて
給与所得かどうかの判定は、
- 自己の計算と危険によらない
- 他人(組織を含む)の指揮監督下にある
かで行うべきで、この対価として支払われたお金は給与所得と解釈してよく、固定制・継続性が要件ではないとしました。
しかも、報酬は大学の定めた報酬規程に従って支払われていた事実があり、この点をもっても、
「本件手当が固定性・継続性を欠いているとの原告の主張は採用できない」
と却下されました。
B.常勤講師との格差があることについて(常勤に認めれているものがないのだから、自己の計算と危険で独立しているという論)
- 非常勤講師も常勤講師も大学が定めたカリキユラムを実施するうえでその大学の教員組織を構成するものであることは共通である。
- ただその地位によって、待遇に格差があることは事実だが、それは所得を分類する基準となる所得の発生様態や性質とは何も関係ない。
給与所得かの判定は、これまで述べてきたように
- 労務提供における計算と危険は誰が負っているか
- 労務提供が使用者の指揮監督下にあるか
でなされるべきであり、処遇が十分でないからといって、給与所得でないとする根拠にはならない、としました。
そして、各種の権限がないことについては、
「カリキユラム編成に関与できないこと、その他大学内部の各種委員会の一員になれないことも同様に雇傭関係の存否を判断するうえで何ら影響を及ぼさない」
とし、必要経費を与えてられないことについても
「必要経費の多寡が所得を分類するうえの基準となっているものとは解されない」
「経費の支出は給与所得控除額では不充分であるかもしれないが、研究費が支給されないからといって、本件手当が給与所得にあたらないとはいえない」
と、非常勤講師の主張を認めませんでした。
C.代替性について
非常勤講師の講義の内容が、専門分野にわたり、第三者との代替性が効かないことについては、
「雇用契約の目的となる労務の種類には、高度な専門性のある労務もあるし、簡単な労務もあるので、それをもって雇用契約でないとはいえない」
(たとえば、高度の専門性が要求され、本人にある程度の自主性が認められる国会議員の歳費や普通地方公共団体の議会の議員の報酬なども給与所得とされている)
さらに、同様の主張は常勤講師にもいえるだろうとして、非常勤講師だけが特別でないとし、「雇用関係を否定する根拠にならない」と判断しました。
D.雑所得について
大学の非常勤講師の講義は「講演料と同じ性質のも(だから雑所得になるという主張)」という主張については、
「非常勤講師は、大学の目的に則り、当該大学の定めたカリキユラムを実施する教員組織の構成員として講義を行なうものであり、この点において各種の講演とは根本的に異なる」
として、これも一蹴されました。
反対に、事業所得に認められるには、この2点は絶対
大事なので繰り返しますが、給与所得の判定のポイントは
- 労務の提供が自己の計算と危険によらない
- 他人の指揮監督下に置かれて、その対価として受取る報酬
の2つです。
逆にいえば、
- 労務の提供が自己の計算と危険によって
- 他人の指揮監督下に置かれないで受取る報酬
が事業所得となります。
その具体的な基準を表したのが、消費税1-1-1にある
- その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
- 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
- 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
なのです。
その他の要素、たとえば事例にあるような待遇の格差があっても、それは雇用関係かどうかには関係ないポイントなのです。
まとめ
この記事では、非常勤講師の報酬が「雑所得」か「給与所得」かの判例をもとに、その判断のポイントについて解説してきました。
給与か事業所得かは
- 専門性があるから代替性が効かないということは雇用契約とは関係ない
- 処遇の格差も関係ない
- 給与が継続的にもらえないとか、固定性であるかも関係ない(逆にいえば変動であっても関係ないということです)
というとろこも参考になります。
「報酬を出来高制にすれば業務委託契約が成り立つ」と勘違いしている人もいらっしゃるので気をつけたいところです。
給与か事業所得(請負契約・業務委託契約など)は、シンプルに
- 自己の計算と危険はどうか
- 指揮監督下にあるか
という2点に絞られます。
外注化をする場合は、この2点に気をつけて契約を結びましょう。
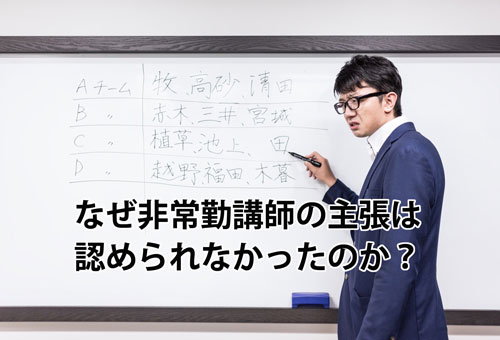



コメント